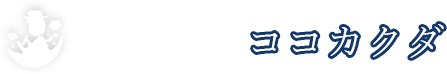本文
住吉神社(枝野)
概要
すみよしじんじゃ(えだの)

この住吉神社は、嘉暦元年(1326年)に摂津国(現大阪市)の住吉大社から分祀されたもので、かつては「嘉暦明神」または「枯木明神」と呼ばれて信仰されたという。
現在の社殿は昭和3年(1928年)に建造されたもので、本殿は流造(ながれづくり)様式である。
住所
角田市枝野字郡山5
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
電話
0224-63-2120 角田市商工観光課
Fax
URL
詳細情報
- 祭神は底筒男命(そこつつおのみこと)、中筒男命(なかつつおのみこと)、表筒男名(うわつつおのみこと)の三神で、国家・航海・漁業の守り神として、また商売繁盛・縁結び・子授けの神として崇敬を集めている。
- 社殿の西側には絵馬殿と神輿殿があるが、特に絵馬殿は江戸時代中期の正徳2年(1712年)建造の旧拝殿を移築したもので、建造より300年以上が経過する貴重な建造物である。
- 中には奉納された5枚の大絵馬がある。
- 境内には樹齢700年の老杉があり、御神木として祀られている。
- その境内には、笠松地区から移設された蚕神様社の小祠をはじめ、養蚕にまつわる巳待碑、猫神、蚕養嶺神などの碑、青麻大権現、湯殿山などの信仰碑が多く残る。
- 住吉神社の敷地は、奈良時代の伊具郡衙(役所)跡かそれに付随する寺院跡と推定される郡山遺跡の一部にあたる。郡山遺跡の発掘調査では、大型の掘立柱建物跡や大溝が確認されており、時期は多賀城創建(神亀元年=724年)以前の、7世紀末から8世紀初頭にさかのぼる可能性が強いとされる。当時の建造物に使われていた礎石の一部は、住吉神社の社殿礎石として転用されている。
アクセス/角田駅から車で20分。