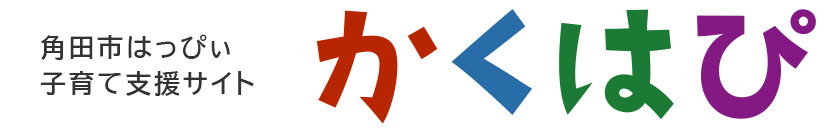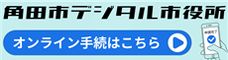本文
児童手当
児童手当とは
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給される手当です。
児童手当の受給資格者
日本国内に居住し、児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(原則として所得の高い方)に支給されます。
支給額と支給月
| 区分 | 手当額(月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子、第2子※ 15,000円 第3子以降※ 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 |
第1子、第2子※ 10,000円 第3子以降※ 30,000円 |
| 支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月 | 12月~1月分 | 2月~3月分 | 4月~5月分 | 6月~7月分 | 8月~9月分 | 10月~11月分 |
偶数月の10日に前月までの分を支給します(偶数月の10日が、土日、祝日の場合は、直前の平日に支給します)。なお、定期払の支払通知書はお送りしませんので通帳の記帳等でご確認ください。
認定請求手続き
初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、事由が発生した日の翌日から15日以内に認定請求のお手続きが必要です。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先でお手続きをしてください。
変更手続き等
次の場合には、お手続きが必要です。
<登録内容の変更>
○住所変更(市内での転居)
○氏名変更
○振込口座の変更(受給者名義のものに限る)
<児童数の変更>
○第2子以降の出生、養子縁組等により監護する児童が増えた場合
○児童の施設入所、離婚等により監護する児童が減った場合
○18歳年度末を経過した後22歳年度末の子についての監護相当・生計費負担状況に変更があった場合
<受給資格の消滅>
○受給者が市外へ転出する場合
○受給者が公務員になる場合
○児童の施設入所、離婚等により受給者が監護する児童がいなくなった場合
その他お手続きが必要になる場合がありますので、対象児童や受給者の状況に変更があった場合は、お問い合わせください。
令和6年10月分からの児童手当が改正されました
|
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
|
|---|---|---|
| 支給対象受給者 | 中学校修了(15歳に到達した年度末)までで、国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代(18歳に到達した年度末)までで、国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 手当月額 |
・3歳未満:月額15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降:月額15,000円 ・中学生:月額10,000円 ・所得制限以上:月額5,000円 ・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:月額15,000円 第3子以降:月額30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降:月額30,000円
|
| 多子加算のカウント対象となる児童の年齢 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
| 支払回数 |
年3回(6月、10月、2月) ※各前月までの4か月分を支給
|
年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 制度改正後の初回は、12月支払分(10月・11月手当)からになります。 |
令和6年10月からの児童手当制度改正に関するQ&A
| Q1 制度改正はいつからですか? |
|---|
|
令和6年10月分の児童手当から反映されます。制度改正後は、2か月ごとの支給となり偶数月の10日に児童手当を支給しますので、令和6年10月・11月分は令和6年12月10日に支給予定です。(偶数月の10日が、土日、祝日の場合は、直前の平日に支給となります。) |
| Q2 児童手当の請求者は父母のうちどちらですか? |
|---|
| 子の主たる生計維持者(所得が高い方)が請求者になります。 |
| Q3 第3子以降の支給額の加算とは何ですか?また、多子カウントは何ですか? |
|---|
|
請求者が養育している子が3人以上いる場合に、3人目以降の支給対象児童の児童手当が増額されます。請求者が養育している子が何人いるか数えることを多子カウントと言います。制度改正前は、請求者が監護し、かつ、生計を同じくしている高校生年代以下の子がカウント対象でしたが、制度改正後は、請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がカウント対象に加わります。ただし、父母等から独立して生計を営んでいる場合は、多子カウントの対象外です。 |
| Q4 監護相当・生計維持の負担についての確認書を提出するのはなぜですか? |
|---|
|
多子カウント対象者の変更に伴い、新たに第3子以降の支給額加算対象になるかを判定するため、請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の有無の確認が必要ですので、ご提出をお願いします。 |
| Q5 新たに児童手当の支給対象となる子とは? |
|---|
| 請求者が監護し、かつ、生計を同じくしている高校生年代の子が、新たな支給対象となります。また、監護・生計要件を満たせば別居や就職していても支給対象となります。なお、請求者が子と別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。 |
| Q6 監護とは何ですか? |
|---|
|
子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることを言います。子の面倒を見て育てている状況なら監護をしているとみなされます。 (参考:監護・生計要件を満たさない場合) 請求者がこの子を放置・虐待し、監護していないと判断される特段の事情を有する場合や、子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。 |
| Q7 生計費の相当部分の負担とは何ですか? |
|---|
| 生計費の相当部分の負担とは、子が請求者の収入により、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことを言います。なお、仕送りの内容が金銭的ではなく、食料費・生活必需品の場合もその仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、生計費の相当部分の負担をしているものとみなされます。 |
| Q8 子と一緒に住んでいないが、住民票上は同住所の場合、別居となりますか? |
|---|
| 子の同居・別居については、原則として住民票上の住所で判断します。したがって、子の住民票上の住所が父母等と同一の場合は同居となります。 |
| Q9 子が進学または就職のため別居している場合、児童手当はどのように扱われますか? |
|---|
| 高校生年代以下の子の場合は、請求者がその子を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は、児童手当の支給対象です。認定請求の際、別居監護申立書の提出が必要です。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の場合、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしていれば、多子カウントの対象となります。 |
| Q10 子が婚姻や出産した場合(子が児童手当を受給している場合を含む)、児童手当はどのように扱われますか? |
|---|
| 高校生年代以下の子の場合は、婚姻・出産に関わらず、子を監護し、また、生計を同じくしている場合は、児童手当の支給対象です。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の場合、婚姻・出産に関わらず、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分を負担していれば、多子カウントの対象となります。 |
| Q11 子が海外留学をしている場合は、児童手当はどのように扱われますか? |
|---|
|
高校生年代以下の子の場合、請求者が子を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は、日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内は、児童手当の支給対象となります。認定請求の際、在学証明書等の書類及び別居監護申立書の提出が必要です。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の場合は、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしていれば、日本国内に住所を有しなくなった日から4年以内は、多子カウントの対象になります。認定請求の際、在学証明書等の書類の提出が必要です。 |
| Q12 子が児童守る施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、児童手当はどのように扱われますか? |
|---|
| 高校生年代以下の子の場合、原則として施設の設置者や里親などに児童手当が支給されるため、父母等は受給できません。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の場合は、多子カウントの対象になりません。 |