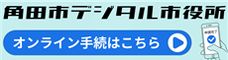本文
【平成9年~20年度生まれの女性の方へ】子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種が条件付きで延長します
子宮頸がん予防ワクチン(キャッチアップ接種)の経過措置について
現在、従来の定期接種の対象者に加えて、令和4年4月から令和7年3月末まで、接種の機会を逃した方のための「キャッチアップ接種」を実施しています。
令和6年夏以降、需要の大幅な増加によってワクチンが限定出荷されたことを踏まえ、下記に該当する人に限り、公費で接種が完了できるよう経過措置を設けることになりました。接種を希望する際は早めに接種開始されることをおすすめします。
経過措置の対象者と条件について
(1)【キャッチアップ接種対象者】平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれで、令和4年4月から令和7年3月までの間に1回以上接種していて、接種が完了していない人。
(2)【定期接種対象者】令和6年度高校1年生相当である平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれで、令和4年4月から令和7年3月までに1回以上接種していて、接種が完了していない人。
※キャッチアップ接種開始前(令和4年4月以前)に接種を受けていても、キャッチアップ接種期間中(令和4年4月から令和7年3月まで)に1回も接種していない場合や令和7年4月以降に1回目を接種する場合は経過措置の対象となりませんのでご注意ください。
経過措置期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
経過措置についてのチラシ
キャッチアップ経過措置チラシ(厚生労働省)<外部リンク>
高校1年相当の女の子と保護者の方への経過措置チラシ(厚生労働省)<外部リンク>
キャッチアップ接種について
HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、平成25年6月厚生労働省通知に基づき積極的な接種のお奨めを差し控えておりましたが、令和3年11月で同通知が廃止されました。
この間、積極的な接種のお奨め差し控えにより接種機会を逃した方(平成9年度から平成20年度生まれの女性)に対して接種機会を確保するため、定期接種の対象年齢を超えて公費の助成により接種を行う「キャッチアップ接種」を実施しています。
ヒトパピローマウイルス感染症とは
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
ワクチン接種の効果
HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
ワクチン接種の副反応
|
発生頻度 |
ワクチン:サーバリックス |
ワクチン:ガーダシル |
ワクチン:シルガード |
|---|---|---|---|
|
50%以上 |
疼痛・発赤・腫脹、疲労感 |
疼痛 |
疼痛 |
|
10~50%以上 |
掻痒、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など |
腫脹、紅斑 |
腫脹、紅斑、頭痛 |
|
1~10%未満 |
じんましん、めまい、発熱など |
掻痒・出血・不快感、頭痛、発熱 |
浮腫性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |
| 1%未満 | 注射部位の知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 硬結、四肢痛、筋骨格硬直、腹痛・下痢 | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血種、倦怠感、硬結など |
|
頻度不明 |
四肢痛、失神、リンパ節症など |
疲労、倦怠感、失神、筋痛・関節痛、嘔吐など |
感覚麻痺、失神、四肢痛など |
その他、接種部位のかゆみや出血、不快感のほか、疲労感や頭痛、腹痛、筋肉や関節の痛み、じんましん、めまいなども報告されています。
まれですが、以下のような重い症状が報告されています。
- 呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)
- 手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群という末梢神経の病気)
- 頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎(ADEM)という脳などの神経の病気)
定期接種の対象者
角田市に住民票のある小学6年生から高校1年生相当年齢の女子
※【平成9年度生まれ~平成20年度生まれまでの女性の方へ】
平成9年度~平成20年度生まれまで(誕生日が1997年4月2日~2009年4月1日)の女性の中に、通常のHPVワクチンの定期接種の対象年齢の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。
まだ接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。
接種間隔
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 標準的な接種間隔 |
|---|---|---|
| サーバリックス(2価) | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
| ガーダシル(4価) | 3回 |
2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
| シルガード(9価) | 2回 |
※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 2回目:1回目の接種から6か月後 |
| 3回 |
※1回目の接種を15歳になってから受ける場合 2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
接種費用
上記の対象者が接種期限までに規定の回数と間隔で接種する場合、接種費用は無料です。
接種場所
| 実施医療機関 | |
|---|---|
| 金上病院 | 高山内科胃腸科医院 |
| 同済病院 | 名取医院(9価ワクチンのみ実施) |
| 仙南病院 | 丸森町国民健康保険丸森病院 |
| 三澤医院 | 山本医院 |
※必ず事前に医療機関に電話などで予約してから受けてください。
※かかりつけ医が市外の医療機関の場合、実施できる医療機関かどうかの確認をさせていただきますので健康推進課までお問合せください。
持ち物
・予診票
・母子健康手帳
・健康保険証 等(住所、年齢が確認できるもの)
※母子健康手帳を紛失した方は子育て支援課より再交付を受けてください。母子手帳の再交付には時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
※予診票を紛失した場合は健康推進課窓口で再発行できます。窓口で直接お渡しいたしますので母子健康手帳をお持ちの上、窓口までお越しください。
保護者の同伴について
接種当日は保護者同伴が原則となりますが、13歳以上の方の場合は、保護者が同伴しない場合であっても保護者が署名した「同意書」と「予診票」を医療機関へ提出することで接種が可能です。
保護者が同伴しない場合の必要書類は、健康推進課の窓口で直接お渡しいたします。母子健康手帳をお持ちの上、窓口までお越しください。
HPVワクチンに関する相談先一覧
HPVワクチンに関してのご相談は以下をご参照ください。
■接種後に、健康に異常があるとき
まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。
各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関<外部リンク>」を選定しています。
協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
■不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき
各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口<外部リンク>」を設置しています。
■HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。※令和4年4月1日から電話番号が変わりました
電話番号:050-3818-2242
受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
■予防接種による健康被害救済に関する相談
HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度<外部リンク>」のページをご覧ください。