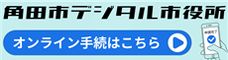本文
国民健康保険の各種制度
こんなときには支給されます(あとで払い戻されるもの等)
次のような形でいったん医療費を全額負担した場合、後日申請により払い戻しが可能です。
- 事故や急病等でやむを得ずマイナ保険証または資格確認書を使わないで診療を受けた場合
- 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
- 医師が必要と認めたギプス、コルセット、輸血の生血代など
- 海外で診療を受けたとき
マイナ保険証または資格確認書、領収書、医師の診断書および世帯主の方の口座番号がわかるものをお持ちになり市民課保険年金係で申請してください。審査後払い戻しいたします。
入院中の食事代
国保加入者全員の所得や住民税の課税状況で入院中の食事代の負担額が変わります。
|
1食あたり (令和7年4月1日から) |
1食あたり (令和7年3月31日まで) |
|
| (1)住民税課税世帯 | 510円 | 490円 |
|
(2)低所得者2 (住民税非課税世帯) |
240円 190円) |
230円 180円) |
|
(3)低所得者1 (住民税非課税世帯 |
110円(変更なし) |
110円 |
(2)、(3)に該当する方で入院をするときは、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は、市民課保険年金係へ資格確認書をお持ちになって「限度額適用・標準負担額認定証」の申請をし、医療機関に認定証を提示します。
※入院時の食事代は高額療養費の支給対象になりません。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
| 所得要件 | 区分 | 限度額 |
|---|---|---|
| 901万円を超える | ア | 212万円 |
| 600万円を超え901万円以下 | イ | 141万円 |
| 210万円を超え600万円以下 | ウ | 67万円 |
| 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 2(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
| 1(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 低所得者2 | 31万円 | |
| 低所得者1 | 19万円 | |
※同一世帯に70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる場合、70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後に残った自己負担額に、70歳未満の人の自己負担額をあわせて70歳未満の人の限度額を適用します。
※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
出産育児一時金
国保に加入されている方が出産した場合(妊娠85日以上の死産、流産も含む)に支給されます。
※他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、6か月以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。
支給される額
出生児一人につき50万円を世帯主の方へ支給します。
直接支払制度
国保から医療機関に直接支払われます(医療機関での手続きが必要)。
ただし、上記の金額を下回った場合は、世帯主の申請により差額分が支給されます。
また、直接支払制度を利用されない場合も、世帯主の申請により支給されます。
申請に必要なもの
- 出産した医療機関等の領収書の写し
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主の方の口座番号がわかるもの
その他支給されるもの
葬祭費(5万円)
国保に加入されている方が亡くなった場合に支給されます。死亡届を提出の際に「葬祭を行う者」の申請により支給されます。
申請手続きに必要なものは、喪主の方の口座番号がわかるもの、会葬礼状およびマイナ保険証または資格確認書です。
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急性があって、入院、転院のため車などを利用した場合に、その費用が支給されます。
申請手続きに必要なものは、世帯主の方の口座番号がわかるもの、医師の意見書、領収書およびマイナ保険証または資格確認書証です。
※各種届出には本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。