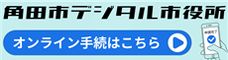本文
「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の施行について
更新日:2025年1月21日更新
本市の豊かな自然環境や美しい景観及び地域住民等の安全安心で快適な生活環境と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るため、事業者の手続きその他必要な事項を定め、もって自然環境等に配慮した、災害のない豊かで持続的な地域社会の発展に寄与することを目的として、「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定し、令和7年7月1日から施行します。
これにともない、市内で再生可能エネルギー発電事業を行う場合、手続きが必要になります。
これにともない、市内で再生可能エネルギー発電事業を行う場合、手続きが必要になります。
適用となる事業
発電出力10kW以上の事業
ただし、次の太陽光発電設備の設置は、適用外となります。
・建築物の屋根、屋上又は壁面へ設置するもの
・抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地に設置する発電出力50kW未満のもの
ただし、次の太陽光発電設備の設置は、適用外となります。
・建築物の屋根、屋上又は壁面へ設置するもの
・抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地に設置する発電出力50kW未満のもの
抑制区域について
災害の防止又は自然環境等の保全のため、特に配慮が必要と認められる区域を「抑制区域」として指定しています。
事業区域の一部でも「抑制区域」が含まれている場合、市長は事業に同意しません。
抑制区域
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域
(7) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(8) 森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内の区域を除く。)
(9) 自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項の自然環境保全地域又は同条例第23条第1項の緑地環境保全地域
(10) その他市長が必要と認める区域
事業区域の一部でも「抑制区域」が含まれている場合、市長は事業に同意しません。
抑制区域
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域
(7) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(8) 森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内の区域を除く。)
(9) 自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項の自然環境保全地域又は同条例第23条第1項の緑地環境保全地域
(10) その他市長が必要と認める区域
住民等への説明会について
・この条例の適用となる事業を実施しようとするときは、市へ協議する前に、住民等に対し、事業計画に関する説明会を開催しなければなりません。
・事業者は、説明会において住民等の理解を得られるように努めなければなりません。
・住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業内容について意見を申し出ることができます。
・事業者は、意見の申出があったときは、意見に対する見解を記載した書面を作成し、住民等に通知のうえ、誠意をもって協議しなければなりません。
・事業者は、説明会において住民等の理解を得られるように努めなければなりません。
・住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業内容について意見を申し出ることができます。
・事業者は、意見の申出があったときは、意見に対する見解を記載した書面を作成し、住民等に通知のうえ、誠意をもって協議しなければなりません。
市との協議について
この条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、この事業に着手しようとする日の90日前までに、市に協議書を提出しなければなりません。
同意
この条例の適用となる事業を実施しようとするときは、市長の同意を得なければなりません。
事業区域の一部でも抑制区域が含まれている場合は同意しません。
事業区域の一部でも抑制区域が含まれている場合は同意しません。
事業実施の手引き
条例の施行日
令和7年7月1日