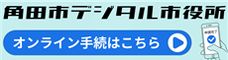本文
後期高齢者医療制度について
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの一定の障害がある方
それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから、自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
医療機関での窓口負担
医療機関にかかるときは,「後期高齢者医療制度」のマイナ保険証、紙の保険証または資格確認書を提示します。
医療機関等での窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の住民税の課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
医療費の増大や現役世代の負担抑制のため、令和4年10月1日から、一般所得者等のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割となりました。
窓口負担割合が2割となる方には、外来診療の負担増加額を抑える配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)
資格確認書
令和7年8月1日からの後期高齢者医療資格確認書は、被保険者一人に1枚交付されます。医療機関等を受診する際は、資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。
資格確認書は1年更新となっており、毎年8月1日に新しいものに切り替わります。令和7年7月中旬より、新しい資格確認書(オレンジ色)を順次発送しております。
- 令和7年8月1日からの資格確認書はマイナ保険証をお持ちの方にもお送りしています。
- 病院・薬局などでお支払いいただく窓口負担の割合は、毎年8月1日に判定を行うため、資格確認書も毎年更新されます。今回お送りした資格確認書は、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者および70歳から74歳の方の令和6年中の所得等を基に判定しております。
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちだった方は、資格確認書に「限度区分」が記載されます。そのため、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されません。
- 現在お使いの保険証(みどり色)、資格確認書(ピンク色)については、有効期限が令和7年7月31日となっておりますので、8月1日以降に角田市役所市民課保険年金係窓口へお返しいただくか、ご自身での処分(個人情報が記載されていますので、細かく裁断するなどして破棄してください)をお願いいたします。
なお、今回お送りした資格確認書(オレンジ色)に負担割合の「発効期日」が記載されていないものがあることが判明いたしました。同期日が未記載であっても、医療機関等での使用には支障はありませんので、8月以降に医療機関等を受診される際は、7月中にお手元に届く新しい資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。また、角田市役所市民課保険年金係窓口でお申し出いただければ、「発効期日」を記載したものとお取り替えしております。
【令和8年8月以降の対応について】
令和8年8月以降マイナ保険証を登録している方は、「資格情報のお知らせ」を交付します(申請の必要はありません)。医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、従来の資格確認書と同様に受診できます。(※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。)マイナ保険証を登録していない方は、資格確認書を交付します(申請の必要はありません)。
マイナ保険証の登録を解除する方は角田市役所市民課保険年金係窓口で申請すれば、解除ができます。解除により、令和8年8月以降は資格確認書を交付します(解除の申請をすれば、交付の申請は必要ありません)。
詳細は、宮城県後期高齢者広域連合HPをご覧ください。
宮城県後期高齢者広域連合のサイトへ<外部リンク>
代理人による資格確認書等の申請について
後期高齢者医療制度の資格確認書に係る申請を代理人(同居以外の別世帯の方)が届出をする場合は、手続きに必要な書類に加えて委任状が必要です。
※委任状は必ず、本人(委任者)が全文自筆でお書きください。病気その他の理由により、委任者本人が自筆で署名できない場合は、事前に保険年金係へ相談してください。
下記から委任状様式をダウンロードすることができます。
保険料と納付方法
保険料
保険料については、県全体で必要となる医療費をまかなえるよう、その1割を被保険者全員で負担することになります。保険料は広域連合ごとに条例で定められ、2年ごとに見直しされます。
令和6・7年度の保険料
宮城県の保険料率
所得割率 9.28%
均等割額 47,400円
※令和6年度における所得の少ない者に係る所得割率の特例として、基礎控除後の総所得
金額が58万円を超えない者に対しては、軽減用所得割率8.72%を用いて算定する。
上限額 80万円
※令和6年度における保険料の賦課限度額の特例として、以下の対象者は73万円となる。
1.施行期日の前日までに後期高齢者医療の被保険者であった者
2.障害認定を受け、後期高齢者医療の被保険者である者
保険料は全員が納めることになります。
納付方法
原則として年金から天引きされます。
ただし、年金額が少ない方や年度途中に年齢到達等で制度に加入した方等は、納付書により納めていただく場合もあります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
軽減
所得が低い方や会社の健康保険などの被扶養者であった方など一定の条件を満たす場合、保険料が軽減されます。
運営
都道府県単位で、すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
市町村の役割
- 保険料の徴収
- 申請者届出の受付
- 資格確認書の引渡しなどの窓口業務を行います。
広域連合の役割
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付などを行います。
宮城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>